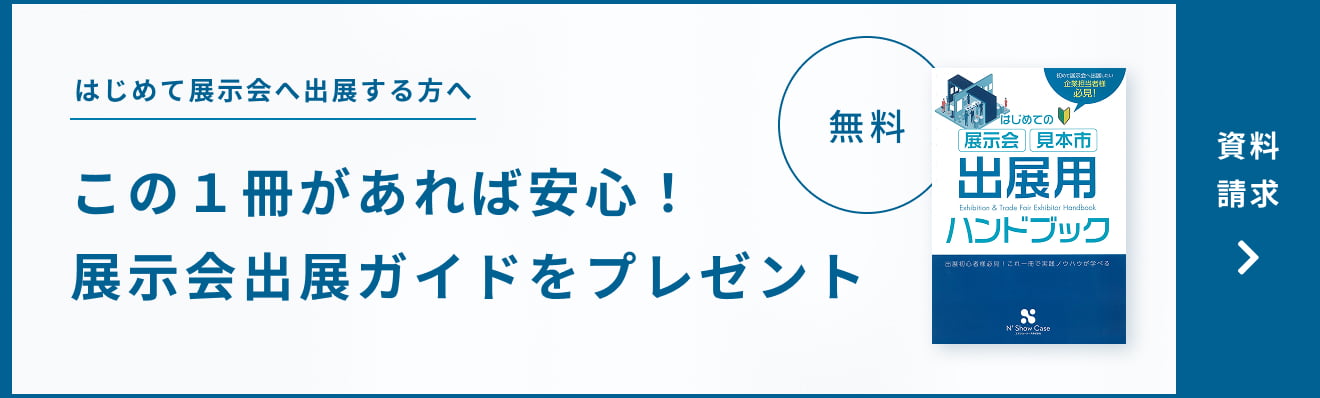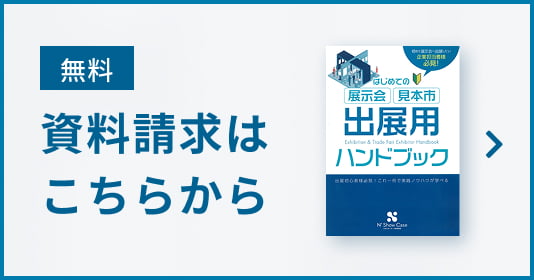多くの企業にとって、展示会への出展は新規顧客の獲得、ブランド認知の向上、市場動向の把握など、ビジネスを飛躍させるための重要な戦略の一つです。しかし、多大な費用と時間を投じて出展したにもかかわらず、「思ったような成果が出なかった」「成功といえるのか曖昧なまま終わってしまった」という声も少なくありません。
展示会は、単に出展することに意義があるのではなく、明確な目的を設定し、それを達成するための戦略的な取り組みが不可欠です。
そこで今回は、展示会が失敗してしまう原因や、成功に導くためのポイントなどを詳しく解説します。
展示会の成功とは何か

展示会の成功とは、単に多くの来場者と名刺を交換することではなく、自社が設定した目的に対して具体的な成果が得られることです。例えば、新規顧客の獲得、製品の認知向上、パートナー開拓、既存顧客との関係強化など、目的によって成功の定義は異なります。
重要なのは、出展前に目的を明確にし、それに沿ったブース設計・接客・資料・フォロー体制を整えることです。展示会は単なるイベントではなく、営業・マーケティング活動の一環です。
展示会中の対応だけでなく、事前準備と事後フォローを含めた一連の活動が成果につながったとき、初めて「成功した展示会」といえます。
展示会が失敗するよくある原因
展示会への出展が失敗してしまう原因としては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 目的が曖昧なまま出展している
- ターゲットを設定していない
- 事前告知をしていない
- ブース設計が目を引かない
- スタッフの教育が不足している
- 事後フォローが遅い
目的が曖昧なまま出展している
展示会の出展目的が不明確なままでは、訴求内容や評価軸が定まらず、成果に結びつきません。「とりあえず出る」「例年出しているから」といった理由で準備を進めると、ブース設計や資料、接客も場当たり的になりがちです。
結果として、来場者に何を伝えたいのかが伝わらず、記憶にも残らない展示になります。出展前に「何のために出るのか」「何を成果とするのか」を明確にすることが不可欠です。
ターゲットを設定していない
誰に向けた展示なのかが不明確だと、訴求内容がぼやけ、興味を引くことができません。特にBtoB分野では、設計・開発、購買・調達、経営層などで関心ポイントが異なるため、すべてに共通する内容では刺さりません。
「誰に」「何を」届けたいのかを具体化し、そのターゲットの課題や関心に寄せたメッセージ設計が必要です。万人向けではなく、特定の相手に届ける視点が欠かせません。
事前告知をしていない
展示会への出展は、出れば人が自然に集まるものではありません。特にBtoBの展示会では、来場者が「どのブースを回るか」を事前に計画して来場することも多いです。
自社サイト、メール、SNS、DMなどを活用し、「どこで・何を展示するか」を事前に周知しておくことが重要です。告知をしないまま出展すれば、せっかくの機会も誰にも気づかれずに終わるリスクがあります。
ブース設計が目を引かない
来場者は限られた時間で多くのブースを回るため、「一瞬で興味を引く工夫」が求められます。ブースのキャッチコピーが抽象的すぎたり、パネルが情報過多・文字が小さいなどの設計ミスがあると、立ち止まってもらえません。
また、導線が悪いと混雑や見づらさが生じ、滞在時間が短くなります。見やすさ、分かりやすさ、入りやすさを意識したブース設計が重要です。
スタッフの教育が不足している
展示会では、ブースに立つスタッフの対応が来場者の印象と成果を大きく左右します。知識が不十分で説明に自信がなかったり、受け身で声をかけられないままだと、せっかくのチャンスを逃してしまうでしょう。
また、説明内容が人によってバラつくと、ブランドへの信頼感も薄れます。対応マニュアルや想定問答を準備し、目的やターゲットに応じた話し方を事前に共有することが成功の鍵となります。
事後フォローが遅い
展示会後の名刺やリードに対する対応が遅れると、相手の関心は急速に冷めてしまいます。せっかく獲得した接点も、フォローしなければ成果にはつながりません。
来場者の記憶が鮮明なうちに、お礼メール、資料送付、個別アプローチを速やかに行う必要があります。特にBtoB商材では検討期間が長いため、リードを育成する視点が重要です。
展示会成功の秘訣【企画・準備編】

展示会を成功させるためには、企画や事前準備が非常に重要です。ここがしっかり固まっていなければ、展示会で思うような成果が挙がらないだけでなく、全体の進行や予算計画などにも大きな影響を与えてしまうでしょう。
企画・準備段階では、以下のポイントが成功の鍵を握っています。
- 目的とターゲットを明確にする
- コンセプト・テーマを設定する
- 事前の告知活動を行う
目的とターゲットを明確にする
展示会出展の成果は、「目的」と「ターゲット」の設定に大きく左右されます。新規顧客の獲得、既存顧客との関係強化、ブランド認知の向上など、目的が曖昧なままでは、訴求内容や評価基準がブレてしまいます。
また、誰に向けて展示するのかを明確にしないと、来場者の関心とズレた内容になり、立ち止まってもらえない原因になります。ターゲットが明確であれば、展示物、キャッチコピー、スタッフのトーク内容まですべてが一貫し、来場者の記憶にも残りやすくなるでしょう。
コンセプト・テーマを設定する
展示会で印象を残すためには、「この会社は何を伝えたかったのか」が明確に伝わる必要があります。その核となるのがコンセプト・テーマの設定です。製品の強みや企業の姿勢を表現するコンセプトを決め、それを起点にブースの設計、キャッチコピー、資料、接客トークまで統一することで、来場者に強い印象を与えることが可能です。
さらに、テーマがあることで準備を進めるうえで判断基準が明確になり、進行の軸がブレなくなります。逆にコンセプトが曖昧だと、「何を伝えたいのかわからない展示」になり、記憶にも残らず、商談につながりにくくなるでしょう。
展示会を営業・マーケティングの場として最大限に活用するためには、明確なテーマ設定が重要です。
事前の告知活動をする
展示会を成功させるためには、事前の告知活動が非常に重要です。事前にどのブースを訪れるかを決めている来場者も多く、告知を行わなければ自社の存在にすら気づいてもらえない可能性があります。
Webサイト、メールマガジン、SNS、FAX、DMなどを通じて「どこで何を展示するのか」「来場するメリットは何か」を伝えることで、事前に興味を引き、当日の集客につながります。展示会はただ出るだけでは大きな成果は期待できないので、自社のブースに来てもらうための告知活動が欠かせません。
展示会成功の秘訣【ブース編】

ブースの設計やデザインは、展示会当日の集客数を大きく左右する重要なポイントです。展示会場における企業の顔ともいえるブースでは、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 来場・回遊しやすい動線設計を意識する
- 会場レイアウトや周辺ブースを考慮して設計する
- 照明や演出を工夫する
来場・回遊しやすい導線設計を意識する
ブースが目立っていたとしても、実際にブース内に来場してもらえなければ意味がありません。どこから入り、どこに目を向け、どこで誰と会話するか、これを意識してレイアウトすることで、来場者の滞在時間や接触率が大きく変わります。
例えば通路側にアイキャッチ展示を配置し、興味を引いたら中央で詳しく説明、最後に名刺交換や資料提供という流れがスムーズです。また、製品に触れられる体験スペースや、導入前後がイメージできる比較展示など、「自分ごと化」を促す設計があると、理解が深まり記憶に残りやすくなります。
動線とは単なる通路ではなく、商談までのストーリーを設計する要素です。
会場レイアウトや周辺ブースを考慮して設計する
ブースを多くの人に発見してもらうためには、単に目立つデザインにするのではなく、会場のレイアウトや周辺ブースの出展状況を考慮して設計することが重要です。
よくある失敗例として、遠くからでも目立つように高さのあるブースを構えたものの、近くに来てみると訴求ポイントが上部にあり視界に入ってこないというケースが挙げられます。近年の展示会は出展者数が増加しており、それに伴って通路幅が狭くなっているため、近くにいると高い部分にある装飾は見上げないと見えなくなってしまいます。
また、自社ブースの周りに大手企業の特大ブースがないか、周辺の小間数はどれくらいなのか、競合他社は近くに出展するのかなどを事前に確認しておくことも重要です。会場のレイアウトや周辺ブースの状況を考慮して、柔軟に設計・戦略を立てましょう。
照明や演出を工夫する
来場者に興味を持ってもらうためには、照明や演出を工夫することが欠かせません。レイアウトや展示内容にこだわったブースを構えても、照度や演出が不足していれば周辺のブースと比較すると見劣りしてしまい、来場者の興味を引くことは難しいでしょう。
照度が不足しているとなった場合、あとから照明を追加することがほとんどですが、中には構造上の問題で追加することができない場合もあります。そのため、ブースのデザインを業者に依頼する場合は、あらかじめ照度に問題がないか確認しておきましょう。
オクタルクスで他社と差別化しませんか?

オクタルクスはブースを構成する柱や梁そのものがLEDで発光する最新のブースシステムです。1680万色のRGBフルスペクトルがシステムを輝かせ、インパクトのあるブースを安価に仕上げることが可能です。オクタルクスのブースを導入したい方は、ぜひエヌショーケースまでご相談ください。
ご相談・お問い合わせはこちら
展示会成功の秘訣【当日・事後編】

来場してくれた人がその後商談や成約につながるかは、当日の対応や展示会後のアフターフォローによって大きく左右されます。せっかく興味を示してくれた来場者を成果につなげるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- スタッフの役割分担を明確にする
- 顧客のフェーズに合わせたアフターフォローをする
- 営業と連携して案件化の導線を作る
スタッフの役割分担を明確にする
展示会当日は限られた時間で多くの来場者に対応する必要があるため、スタッフごとの役割分担を明確にしておくことが非常に重要です。例えば、「呼び込み」「製品説明」「名刺交換・記録」「混雑時のサポート」など、担当を明確にすることで動きがスムーズになり、来場者に対して丁寧で効率的な対応ができます。
全員が同じことをしようとすると対応がバラつき、チャンスを逃す原因になります。事前にフローを共有し、誰がどのタイミングで何をするかを明確にしておくことで、接客の質が安定し、結果として商談率の向上につながるでしょう。
顧客のフェーズに合わせたアフターフォローをする
展示会後のアフターフォローでは、すべての来場者に同じ対応をするのではなく、顧客の検討フェーズに応じたアプローチが重要です。フェーズに応じて提供する情報の内容や深さを調整することで、見込み客を適切に育成でき、無駄なく成果に結びつけることが可能です。
営業と連携して案件化の導線を作る
展示会で獲得したリードを成果につなげるには、営業部門との密な連携が不可欠です。展示会担当が名刺を集めるだけで終わらせず、営業がすぐに動けるような情報整理と引き渡しが求められます。
例えば、来場者の関心度や導入時期に応じてランクで分類し、それぞれに最適な対応方針を決めて共有します。こうした導線が整っていれば、展示会後のフォローがスムーズになり、商談の立ち上がりも早くなります。
ポイントを押さえて展示会を成功させよう
展示会を成功させるには、明確な目的とターゲットの設定、伝わるブース設計、スタッフ対応の質、そして展示会後のフォローまで、すべてを戦略的に設計することが欠かせません。成果を上げるためには、出展を目的にするのではなく、展示会を「営業の起点」として捉え、一連の流れを継続的に改善していくことが重要です。
今回ご紹介したようなポイントを押さえ、展示会への出展を成功させましょう。
展示会への出展に関して、不安や疑問があればエヌショーケースまでご相談ください。これまでの豊富な支援実績をもとに、最適なプランをご提案します。
ご相談・お見積りはこちら